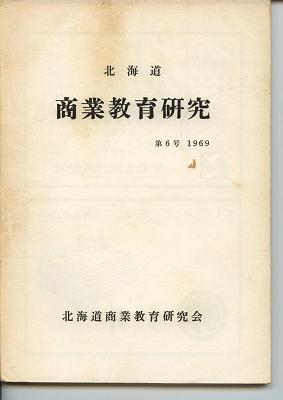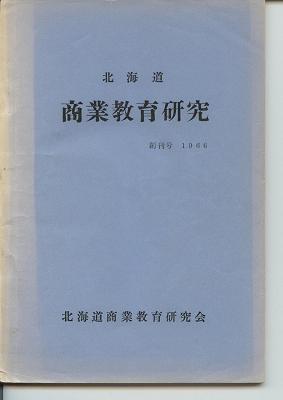
1.商業教育研究の現状と商教研の課題 北海道商業教育研究会事務局
2.日本経済の全体構造と商業学習の意味 浜林 正夫
3.商業教育近代化の方向 横川 義雄
4.後期中等教育再編成と商業教育 浦田 広胖
5.商業教育における学力観 佐藤 善也
6.商業教育の現状 梅木 和朗
7.商業教育の再検討 飯沼 正武
8.商業教育の在り方と教育研究の方法
・第1回含宿研報告にかえて
・鈴木秀一氏講演の内容
・討論の内容
9.教育研究をどうすすめてしいくか 黒田孝郎氏の所論から
10.編集後記
機関誌「北海道商業教育研究」 第1号~第6号
北海道商業教育研究 創刊号(1966年7月15日)
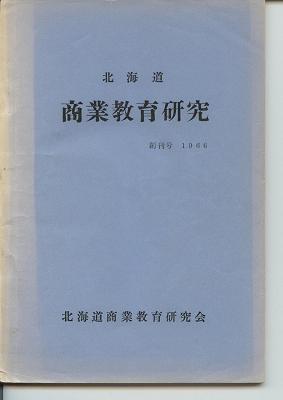
1.商業教育研究の現状と商教研の課題 北海道商業教育研究会事務局
2.日本経済の全体構造と商業学習の意味 浜林 正夫
3.商業教育近代化の方向 横川 義雄
4.後期中等教育再編成と商業教育 浦田 広胖
5.商業教育における学力観 佐藤 善也
6.商業教育の現状 梅木 和朗
7.商業教育の再検討 飯沼 正武
8.商業教育の在り方と教育研究の方法
・第1回含宿研報告にかえて
・鈴木秀一氏講演の内容
・討論の内容
9.教育研究をどうすすめてしいくか 黒田孝郎氏の所論から
10.編集後記
機関誌第1号 巻頭言 北海道商業教育研究会 事務局
(1) 私たちのまわりをみると、商業教育はあっても商業教育研究がまったくないように思います。
それは言い過ぎではないかという人がいるかもしれません。しかし、現実を見ると商業科には、授業をどう進めたらよいかという教育技術にかかわる研究は多いのですが、商業教育の現状を堀り下げ、そのあり方を問うといった研究はほとんどないようです。
もちろん、教育技術の研究が重要ではないなどというつもりは毛頭ありません。授業のヘタな教師は許せない存在であると斎藤喜博氏は言っていますが、たしかに、教師が授業の力量を高めるために指導技術の向上に努めることは重要な任務です。この重要性を百パーセント認めた上でも、それと平行して、いやそれ以上のウェイトをかけて、商業教育のあり方を抜本的に検討することが、いまほど要求されている時はないと思います。
なぜなら、商業教育が直面している壁はあまりにも厚く、数多くの大きな問題を抱えているからです。大学区制が実施され、高校再編成が立案されているいま、商業教育はその存立そのものの意味を問われているといえましょうし、また間もなく提出されようとしている「後期中等教育改革」と、続いて予定される指導要領改訂は、商業教育を制度的にも内容的にも丸ごと転換しようとしています。
この時期こそ、私たち商業教育に当るものは、商業教育の現状をしっかりとらえ、商業教育のあり方や意義を、根底から再検討することが必要だと考えます。残念ながら、問題の重要性にもかかわらず、こうした研究はほとんどされていないのです。冒頭に書いたように、商業教育はあっても商業教育(研究)がまったくないというのはこの意味です。
(2) 戦後日本の教師が進めている自主的教育研究の成果は、民間教育運動の盛況や組合の自主教研蓄積に反映されています。このことは、民間教育研究議団体の機関誌や多くの出版物そして自主教研を総括した「日本の教育」を手にするだけで知ることができます。
では民間教育運動や組合教研の場で商業教育研究がどれだけなされたかを、雑誌とか書籍はもとよりパンフレットの果まで探しまわってみても、まったくないとはいえないにしても、まず皆無に近い状態なのです。次の一文は、商業教育研究の状況を端的に表現しています。
商業教育および水産教育についての報告や論議は、ほとんど全国教研集会でなされていない。こころみに、第9次以降の生産技術分科会の正会員数を調べてみた。9次から14次までの6年間に商業高校からは(9次、11次、13次にそれぞれ1名づつ、14次に3名)6名、水産高校からは(12次1名、14次2名)3名、の正会員がでているだけである水産高校は学校数も少ないのだから、このような数は判るとしても、商業高校は多教あるのに、こう少ないのはどうしてなのだろうか。
技術教育という分科会の構成が商業教育問題を提起しにくいとしたら、青年の教育あるいは教育課程分科会では、商業教育について論じられているのだろうか。各年度の「日本の教育」を調べた限りでは、商業教育について論じられた文章はほとんど見当らないのである。(「国民のための教育の研究実践:技術編」日教組編)
(3) 商業教育になぜこのような教育不在が根強いのでしょうか。この原因を探るのが本旨ではないのですが、一つだけ指摘しなければなりません。それは問題がないから研究が進まないのではなく、山のような問題がありすぎてどこから手をつけてよいか判らないから進まないのだという面があることです。
もう日常化してしまって、問題にしなくなった傾向のある大問題のかずかず、多科目小単位のコマギレ教科内容、検定制度にふり廻される珠算や簿記、女子増加による男女共学の非正常化、低学力層の増大などを、改めてみつめると、ただもう問題の根深さに長嘆息するばかり、どこから手をつけてよいか判らないといった実情があります。だから、これからを改めて問題にしようとすれば、まず五里霧中をさまようのが関の山で、エイ面倒臭い、いまの姿を前提にして、その枠のなかで授業展開を考えようということになってしまうのでしょう。したがって、教育研究は進まないし、問題は頑固に根深くなっていっそう手のつけようがなくなるという悪循環が生みだされているように思われます。
いったいどうすればよいのかと指導要領をみると、ここには現場の悩みからはるかに遠い無味乾燥な官僚的作文がみられます。そればかりか、この作文が法的拘束力を強め、教育内容を強く規制するようになりました。この作文は現場の苦悶に応えるものではないのはもちろん、生徒の明日の可能性をきり開く羅針盤でもありません。
指導要領に忠実であろうとすれば、商業教育は迷路のような袋小路に入りこんでしまうという現実を否定することはできません。指導要領が羅針盤の機能を果さなくなり、教育の航路がはっきりしていないところに、現場の苦悶の救いがないともいえます。もっとも指導要領という一片の官僚的作文で、現場の苦悶が救われると考えるのは甘いことなのでしょう。
羅針盤が有効にに機能しない以上、正しい航路を進めないのは当然です。大切なことはなにか。
それは、私たちがみずからの手で、現場の苦悶に根ざして、私たち自身の羅針盤を日常の教育実践のなかから作りあげることではないのでしょうか。こうした問題意識にたって、日常的に継続的に努力することが、教育課程の白主編成運動なのだと理解してよいのではないでしょうか。
(4) 私たちの研究サークルである商教研は、商業教育のあり方をいろいろな角度から吟味しようとい
う意志で作られたものです。そして我田引水になりますが、東京にも京都にもこの種の研究会は、まだ組織されていないし、恐らく全国的にみても、珍らしい貴重な存在だと断言できるように思います。案外、結成に関与した私たちが考える以上に、画期的な意義があるのかもしかません。でも、全国的にみて珍らしい研究サークルだから貴重だということでなしに、研究の方向と内容が貴重だと評価されるよう、活動を進めたいものです。
本年1月、全道の11校から16名が集まり結成総会を兼ねて、2日間ささやかながらも充実した熱つぽい討議をしました。それらの討議を踏まえ、商教研のこれからの課題を、いくつか提起してみたいと考えます。
第1は、商業教育はなにを目標にするのかを明らかにすることです。「中堅産業人の育成」とか「ミドル・マネージメントの養成」とかいわれるものの内容に検討を加え、商業教育がだれのために行なわれるべきかを明らかにする必要があります。
第2は、商業教育を科学に基づいて系統化する作業を進めることです。ごのために、カリキュラム構成、各科目の教科内容、教科書の内容を抜本的に再検討し、私たちの手で再編成することが必要です。
第3は、技術を商業教育全体にどう位置づけるかを明らかにすることです。珠算、簿記、タイプライテイングなどの技術が商業教育全体にどうかかわっているのかの問題です。商業科の技術教育をどうとらえるのかの点では、綜合技術教育の理念と現実から学びうるものが大きいはずです。
第4は、商業科の生徒の実態に即して、生徒のもつ力を引き出し、可能性を最大限伸ばす教育実践を組織的に進め、経験を相互に交流して、それらの蓄積を共通の資産とすることです。
専門職としての教師は、つねに生徒にコミットしており、その限りで明日の日本にコミットしています。私たちの発想の原点は、いつでも生徒を伸ばすことであって、ここから外れた論議は机上の空論に墜してしまうでしよう。
第5は、私たちの商教研という自主的教育研究サークルを発展させることです。教育研究は、なにものの制約も受けることなく、あくまでも自由な立場で、自主的に進められるべきものであって、これこそが教育研究の魂です。魂のない各種の教育研究会の表面上の盛況にひきかえ、その内容がどんなに貧困かは記すまでもないことです。私たちにいま本当に必要なことは、魂を売らずにサークルの輪を広げ、より広汎な層を結集しながら、生徒たちに責任の果せる正しい商業教育を模索することなのです。
北海道商業教育研究 第2号(1966年12月30日)
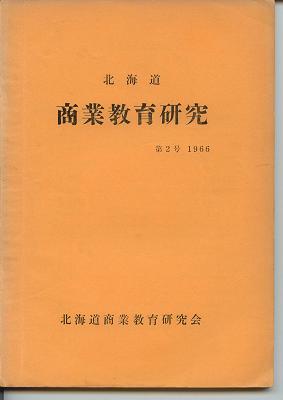
1.教育と生産的労働の結合 竹田 正直
2.後期中等教育再編成の問題点と進路指導の課題 阿久津 昭夫
3.商業教育における教師と生徒のもつ問題点
ならびに商業教育はどんな人間を作るべきか 県立和歌山商業高等学校商業科教員
●特集教科研究(Ⅰ.実践報告・Ⅱ.理論研究)
4.本校における「経済科」レポート指導について 小関 高士
5.実教版「経済(新訂版)」を使っての授業Ⅰ 辺見 武利
6.「商業法規」思いつくまま 小松 信夫
7.「簿記原理」思いつくまま 藤田 昭三郎
8.教科書「経済」(実教版)について 辺見 武利
9.簿記教育近代化にともなう指導上の基本的要素について 藤田 昭三郎
10.計算実務と計数観 舟生 満男
11 商業科における学習指導の問題点 佐藤 善也
12.教育の軍国主義化と勤労学徒の実態 梅木 和朗
13.札商高校における商業教育についての覚書 小野内 勝義
14.会員便り(アメリカ便り・近況報告)
15.編集後記
北海道商業教育研究 第3号(1967年7月28日)
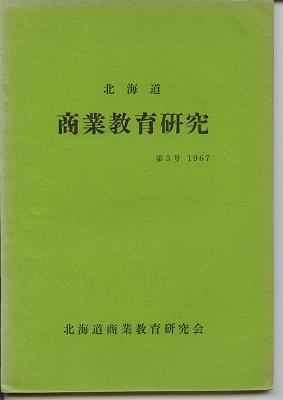 1.後期中等教育問題をどうとらえるか 宮原 誠一
1.後期中等教育問題をどうとらえるか 宮原 誠一
●特集1 商業教育体質改善案をめぐって
2.全商高校長協会の商業教育体質改善の方向を検討する 浦田 広胖
3.商業教育における教育内容現代化の方途 小関 高士
4.全商高校長協会の「改善案」批判 清水 吉二
●特集2 第2回合宿研報告
5.く講演記録>商業教育の新しい構想 浜林 正夫
6.く討論記録>商業教育の現状と課題 -浜林正夫教授を囲んで-
かつて 八百屋や 魚屋の しあわせを 願った 商業教育があったろうか 鬼島 明敏
7.商教研を全国的な活動に発展させよう 藤井 忠信
8.計算実務と珠算検定試験 工藤 昭男
9.商業教科における学習指導の問題嵐(2) 佐藤 善也
10.改良銀行簿記について 佐藤 善也
11 経済の授業覚え書1 浦田 広胖
12.商業高校における就職者の生活と問題 福島 勉
13.「資本論」発刊百年に寄せて 梅木 和朗
14.商業教育関係資料の紹介
15.商業科資料室紹介 小樽商業高等学校 小関 高士
16.編集後期
北海道商業教育研究 第4号(1967年12月26日)
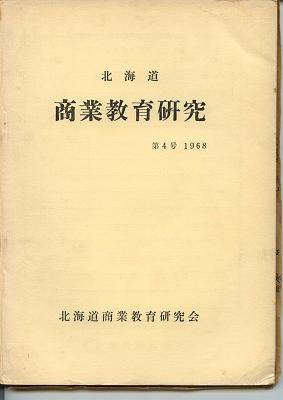 1.国際会計人会議に学ぶもの 久野 光朗
1.国際会計人会議に学ぶもの 久野 光朗
2.教科指導を生き生きとさせるために 海保 孝
3.室蘭商業教研究レポート 事務局
4.高等学校職業教育の多様化問題について
-理産振答申をめぐって- 事務局
5.教育改革研究大阪会議から何を学ぶか 小関 高士
6.商業教育関係資料紹介 その2 事務局
7.商業教育の近代化に即する計算実務の学習内容
その他をどのように改善すればよいか 麻生 晋
8.割賦販売の法解釈的簿記論の一展開 藤田 昭三郎
9.商業高校と「後期中等教育改革」-類型制を中心に- 森下 保道
10.女子教育をめぐって 阿久津 昭夫
11.帝国主義論ノート-発刊50周年に寄せて- 梅木 和朗
12.アメリカ便り第2信「書物と図書館」 松田 芳郎
13.商業教育史(戦前)年表 辺見 武利
14.商業高校の現実「商業科にひそむ問題点」
-質が悪いと言われるが- サンケイ新聞抜粋
15.編集後期
北海道商業教育研究 第5号(1968年8月25日)
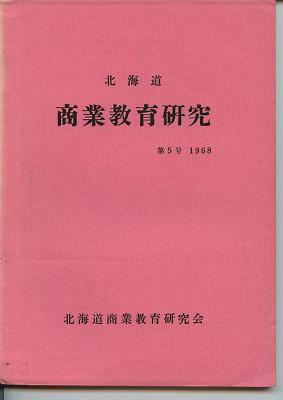 1.経営学を学ぶものへ 古林 喜楽
1.経営学を学ぶものへ 古林 喜楽
2.函館商業教研全体基調講演とその検討 事務局
3.第3回合宿研究会報告
4.高校多様化の問題点 貿易課設置をめぐって
兵庫県立神戸商業高等学校有志
5.商業一般をどう教えて行くか 清水 吉二
6.商業教育における労働関係科目の構想 佐藤 善也
7.文書実務の授業について 商業教育の問題点 藤田 実
8.商業教科における学習指導の問題点
実務的科目を中心として(3) 佐藤 善也
9.教材としての電子計算機について 小関 高士
10.調査報告「企業における電子計算機導入の一例
丸三鶴屋ぼばあい」 浦田 広胖
11.商業教育関係資料紹介 事務局
12.編集後期
業教育研究 第6号(1969年)